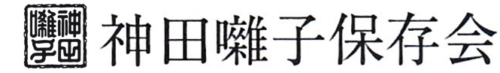第三章 祭り囃子としての神田囃子
(一) 神田囃子保存会の発足
(イ) 神田囃子の名について
(ロ) 新井喜三郎について
(ハ) 初代長谷川金太郎
(ニ) 二代長谷川金太郎
(ホ) 神田囃子保存会の発足
〔青山啓之助の周辺〕
(ヘ) 鈴木忠治
(ト) 吉村長吉
(二) 戦後の保存会
(イ) 祭りの復活
(ロ) 保存会の状況
(ハ) 鼓友会
(ニ) 広尾の稽古場
(ホ) その他の稽古場
(ヘ) 東京都無形文化財指定に向けて
(ト) 無形文化財指定
(チ) 指定後の活動
・正月の奉納
・舞台での活動
(リ) 千代田区囃子教室
(ヌ) 音の記録
(ル) 現会長の就任―昭和四十年
(ヲ) ハービーマンとの共演
(ワ) 稽古場の移動
(カ) 鞆絵組
(ヨ) 三越東都のれん老舗の会
(タ) 伊勢遷宮式
(レ) 国立劇場出演
(ソ) 千代田区囃子教室
第三章 祭り囃子としての神田囃子
(一) 神田囃子保存会の発足
(イ) 神田囃子の名について
江戸の祭り囃子は、葛西に起こったものと言われている。その事は、前章で述べたが、それでは、いつ頃から『神田囃子』という呼び名が出来たのであろうか。化政期〔一八〇〇年頃〕に作曲された清元『神田祭』の中に、神田囃子の名が出て来るが、果して、この頃からであろうか。おそらく、もっとそれ以前からではあるまいか。それは、江戸で最も大きな祭礼として知られた神田祭に、山車・屋台などで囃子が演じられるようになった頃までさかのぼるのではあるまいか。江戸で最も盛んな神田祭に″きほひょく″ 粋に囃されたので、神田っ子達に歓迎され、自分達の囃子として『神田囃子』と呼ばれたに違いない。しかし、その当時の神田囃子がどの様なものであったか、今とどの位違ったものであったのかは分からない。
当時の囃子方は、大部分が江戸近郷の葛西地区の人々であった。彼らは、ほとんどが農民だったが、徐々に、神田に住む職人たちも習い覚えるようになり、やがてその囃子にも神田特有の気質、土地柄などが影響を与えて、神田特有の祭り囃子、つまり本当の意味の神田囃子が生まれ育っていったのではなかろうか。もっとも、祭り囃子に限らず、大衆芸能とか民俗芸能とか言うものは、大体この様に派生していくのではないか。
こうして神田の地に定着して行った神田囃子が、主に地元の人に依る囃子となるのも当然の事であった。それが、はっきりとした形として現れたのは、神田囃子保存会設立の時からであった。大正から昭和にかけての事である。
(ロ) 新井喜三郎について
神田囃子の歴史を語るについて、新井喜三郎は、現在名前の判明する当事者として、最も古い人物である。伝説によれば、初代喜三郎が、それまであった江戸囃子を、神田風に組立て直して神田囃子を作り、代々伝えたと言われているが、真偽の程は分からない。今その存在がはっきりしているのは、十五代目といわれる喜三郎である。新井という姓は、明治になってから付けたと思うのだが、代々神田堅大工町に住み、屋根屋職人であったので、屋根屋喜三郎とも言われている。
その十五代喜三郎は、明治三十五年に亡くなっている。享年は分らないが、江戸時代後期から明治の人である事は間違いないであろう。彼は、神田囃子十五世家元と言われているが、普通に言う家元とは少し違うらしい。神田祭に於て、諸々の事柄、特に囃子関係の事を取り仕切る元締的な存在だったようだ。囃子方には、世話人と呼ばれる人が数多くいたが、彼はそれらの上に立って、頭取と呼ばれていた。
祭りの時に、各町から囃子の依頼があると、喜三郎は、それらの世話人を呼び出し、幾組かのグループを作らせて、各町へ使わして審査を受けさせると言う様な事をしていたらしい。又、正月などに獅子舞をする時にも、囃子方は喜三郎の元へ行き、許可を受けねばならず、許可された印として桶胴に丸一の紋の入った布をまいていなければならなかった。この様に権力を持っていたのが喜三郎であるが、一説によると、新井喜三郎は、江戸幕府のお庭番の流れを汲む者であったと伝えられている。大きな権力を持ち、幾分謎めいた彼には、いかにももっともらしい言い伝えではある。
しかし、喜三郎は実際に囃子の演奏などには携わらなかった。家元とは言っても、あくまで興業権を持つ頭取であり、囃子の演奏は、その下の世話人以下にまかせていたのである。思うに、この人物は我々にとって何か伝説の人であり、又不思議な魅力のある人である。
(ハ) 初代長谷川金太郎
前記の通り喜三郎が祭礼の元締として活躍していた頃に、その下で世話人として実際面を取り仕切っていたのが、初代長谷川金太郎であった。人の手配、場所の決定など喜三郎から任されていたのである。しかし、この人物もくわしい事はよく分らない。記録では、喜三郎の高弟子とも書かれているが、喜三郎が実際には囃子をやらなかったらしいのに対して、金太郎は自ら稽古に励み、囃子の技術的な事や伝承に於いて、祭礼などの場での演奏に於て活躍していたのであある。喜三郎の亡き後は、十六世家元となったのである。住所は小網町だったようである。
(二) 二代目長谷川金太郎
二代目金太郎と呼ばれている人は、本名を金吾といった。初代の亡くなった後に、二代目金太郎を継いだのであるが、同時に十七世家元も継いでいる。名前から言っても、常識的に考えても、初代金太郎の実子であると思うのだが、今一つはっきりしない。元来は、神楽の人であったと言われ、当時の神楽師の元締吉村家から数ケ所の場所を預っていた。神楽師は、神楽の他にも祭り囃子を必ず身に付けているが、金太郎もその例にもれず、おそらく初代から受け継いだ神田囃子を身につけていた。年少の頃から身体が不自由だったらしいが、その技倆は大変なものだったらしい。現在の会の長老松永寅二郎は戦前、二代目が笛に乗って一人で囃子をやるのを聞いた事があるそうだ。ただ、笛は吹かなかったようだが、口伝で笛の手はすべて習得していたと言う。御本人から直接聞いたのではないが、葛西囃子の矢作房吉氏は、この金太郎から口伝で笛を教えられたと聞いている。
日本橋蛎殼町に住み、一年中日和下駄、ステッキを愛用し、唐山の着物に半天を羽織った小柄な人であった。囃子等の出演の無い時は、近くの提燈屋で、提燈に字を入れたりする仕事をしていたという事である。

大胴の後 青山啓之助 大胴 二代目 長谷川金太郎 笛 田村左太郎 獅子 鈴木金次郎
前頁は、青山会長宅にNHK大阪放送局で囃子を演奏したときの社中の記念写真であるが、今残っている唯一の金太郎の写っている写真であり、その面影をしのぶ事ができる。又、幸いな事に戦前のSP盤ではあるが、金太郎の四ッの演奏が残っている。その演奏は、実に迫力に満ちたものである。一人で囃子をやってしまったという嘘みたいな話も、なるほどさもありなんと思わせるものがある。
性格的な面では、なかなかに頑固で因業な一面を持っていたようである。当時、囃子に於ては第一人者であったが、弟子を持つ事を嫌ったようである。古い弟子としては、鈴木忠治、志賀直三〔志賀直哉の弟〕、豊島町の箱屋、通称『箱要』さん等わずかである。
この金太郎と青山啓之助グループとの出会いが、その後神田囃子保存会の発足となるのである。それは金太郎自身にとっては、はじめての本格的な弟子の養成であった。今から五十年以前の昔、大正から昭和にかけての頃であった。この弟子達が、一応一人前になった昭和二年、金太郎の意向により、神田囃子保存会が設立される。金太郎にとって、はじめて社中と名のる事が出来る多数の直弟子を持つ事が出来、又その弟子が、神田神社の氏子たちであったという事が、それまで一般に江戸囃子と称されており、神田祭りに於て特に神田囃子と言われていただけで特定の団体などはなかった『神田囃子』に一つの画期をもたらした。言い換えれば、金太郎の自ら受け継いで来た囃子と自分の技倆に対する限りない自信の現れであったのだ。
しかしながら、保存会とは言っても、今の様にすたれかけた伝統芸能を何とか後世に残そうとする様な趣旨の保守的なものではなく、会則などと言う面倒なものもなかった。いわば、長谷川金太郎社中の称号のようなものであったのである。この後、昭和二十三年に没するまで、長谷川金太郎社中の総師として活躍するのだが、その事は、これ以後の章において、その弟子達の活動として述べて行きたい。
(ホ) 神田囃子保存会の発足
〔青山啓之助とそのグループ〕
今もそうであるが、昔から山岳信仰といわれるものがあった。江戸時代以来、関東・東京には、その中心として富士山信仰が盛んであった。人々は、その為のグループを作り、富士登山などをした。富士講と呼ばれた組織である。その富士講が、神田に七講中あったと言われるが、その中の一つに青山啓之助、竹内和吉らのグループがあった。彼らは、富士登山ばかりでなく、町内での集りや行事、祭礼その他に仲の良い集りとして参加してもいたのである。昔は今に比べて娯楽の少ない時代で祭りは最も楽しい出来事であり、神田祭りはその精神面の意味も加わり、人々のそれにかける意気込みは、今とはけた違いのものがあったそうだ。青山、竹内らの富士講の人達もその例にもれず、祭り好きの人であった。その仲間から、囃子を習おうではないかと言う声が上ったのも当然の事であった。その頃、神田祭りの様に多数の人手のいる時の囃子方は、その多くを葛西近辺―当時の東京郊外の人々に頼っていた。青山達は下町の粋の頂点である神田祭りの当事者として、自分たち自身で囃子をやり、後々まで伝えたいと思ったのである。そこで住居も近く、当時の第一人者であった二代目長谷川金太郎を師に迎えたのである。青山、竹内らの富士講のメンバーを中心に十八、九人の人々がその時に集った。長谷川金太郎を迎えての稽古は、神田連雀町の竹内和吉宅で、毎晩七時頃から約六十日間ほど続けられたそうだ。その間に、皆が一通り太鼓の手を覚えたのである。テープはもちろんないし、ノートに書き写す事も許されず、全くの口伝によって稽古を受けたのだ。昔は三味線その他の稽古もすべて、口伝えで教わったのだが、大変な事だったと思われる。
はじめは、半帖〔古畳〕をたたいて稽古したそうだが後始末が大変だったようだ。その時集って囃子を習得した人の中で名前が分っているのは次の人々である。
青山啓之助、竹内和吉、波多睦六、岸平次郎、加世清蔵、塩崎正吉、鈴木金次郎、田代源吾、仁村輝基、左官の源さん
これらの人々は、すべて故人となっている。この中でも青山啓之助は最も熱心な弟子であり、のみこみもよく上達がはやかった。三十代の頃の青山啓之助修業時代であった。彼は、江戸っ子的な性格と共に親分肌の気質から、長老格の竹内と並んで会の中心的存在となった。囃子を始める時に人を集めたり、師匠の世話をするのも啓之助が主に動いたという。その様な状況から、後に神田囃子保存会初代会長に推されたのである。
稽古も進み、一通り覚えて手が動くようになるとどうしても人前で演奏してみたくなる。元気の良い神田っ子たちは、意気揚々としてあちこちへ行った事であろう。
金太郎自身は笛を吹かなかったので、笛吹きには仲間や配下の人を連れて来て稽古していた。おそらく、十五世喜三郎の世話人であった先代金太郎以来のつながりを持つ囃子方が多数いたのだろう。笛吹の中には、佃の池田弥五郎、渋江村の田村佐太郎と言う大名人と呼ばれた人々がいた。彼らがいると、他の人が笛を吹くのをはずかしがって笛を隠してしまったと言われる位の人で、囃子の笛吹きとしてはとびぬけていた人だった。初期の長谷川金太郎社中には、この様な笛吹が手伝いに来たのである。そんな名人の笛で太鼓を叩く事が出来た先輩
達は、それを非常な喜びとしたに違いない。
その後は前述の矢作房吉氏などが笛吹きとして来ていた。矢作さんは八十歳を越えているが現在も活躍している。古代囃子、間物といわれる『神田丸』『階殿』『亀井戸』などの曲を金太郎から受け継いだとも聞いている。
又、社中の鈴木金次郎は、前掲の写真中で獅子舞の装束をしている。囃子と獅子舞、通しは切り離せないものである。保存会でも鈴木金次郎の獅子舞、竹内和吉の子の信治が年少の頃に通しを踊っていた。ただ鈴木の獅子舞は誰から習ったかは分らない。
その頃の金太郎社中の定例行事としては、昭和の比較的はやい時期から、日中戦争の激しくなる十三、四年頃まで神田神社で毎月一日と十五日に奉納囃子を行なっていたという。青山啓之助たちの神田神社に対する信仰の現れであろう。氏子である自分達によって氏神へ囃子の奉納が出来るというのは、先輩達にとって喜びであったろうし、現在の我々にとっても同様である。神田囃子保存会が発足した当時から現在まで、神田神社と保存会は深いつながりがあったと言える。
青山啓之助について、もう一言すると彼は大胴の名人と言われた人であった。その打つ拍子、間はもちろんであるが直接聞いた事のある方の話では、同じ大胴を叩くのになぜあんなに違うのかと不思議になるくらい彼の大胴の音色はすばらしかったそうである。天賦の才なのであろう。それを直接に聞く事が出来ないのは非常に口惜しい事だ。因みに、明治二十二年四月一日生まれ、昭和四十年一月四日没である。
(ヘ) 鈴 木 忠 治
通称”ポンプの鈴木さん…と呼ばれ親しまれた人である。職業が消防士だったからである。長谷川金太郎の高弟の一人として青山啓之助グループが金太郎について囃子の手ほどきを受ける前から、既に金太郎に師事し囃子の道に入っていた。昭和二年、金太郎社中即ち保存会設立後は青山啓之助らと行動を共にして、長くその中心メンバーとして活躍する。特に締太鼓に於て見事な技倆を発揮した。その歯切れのよいばちさばきから、獅子舞の四ツもすばらしいものだった。しかし、それは、自身の勘に頼るばかりでなく、師金太郎の至芸を受け継ぐべく、金太郎の演奏したレコードを何度も何度も聞き返して工夫した結果でもあった。その為、SP盤のレコードを数枚もだめにしたという事である。新しいものを身につけ様とすれば、師匠の芸を盗み取らねばならない厳しい修業の時代のこのような努力には頭が下がる思いがする。技術的な事もそうであるが、演奏の中で囃子全体を盛り上げ相手の締太鼓の調子をも引き上げていったという面に於ても、すぐれた打ち手であった。
囃子を始めたきっかけなどは、よく分らないが金太郎の家と近い所に居たと言うのもその理由の一つらしい。
キングのレコードから、彼の技倆を伺い知る事が出来るのは、我々にとって幸せな事である。八十歳を越えて、十数年前に亡くなられた。
(ト) 吉 村 長 吉
現在、我々が吹いている神田囃子の笛は、吉村長吉の流れを汲むものである。
吉村は、戦前まだ少なかった大学出の学士であった。東京電力に勤める傍ら、神楽、囃子を手掛けていた。東京の神楽師の大元締め吉村家の次女と結婚し、吉村姓を名のるのだが、結婚する以前から神楽を始めていたと言う。近眼ということもあって立役よりも囃子方、特に笛を習い、その才を発揮した。吉村家に入った後は、神楽の名手と言われた目黒の加藤氏について神楽の笛を研究した。
二十五歳の頃、昭和の初め頃であった。その当時、神楽の笛吹で上手な人々は、技術の練磨のために長唄なども習ったそうであるが、吉村も師の紹介で、本郷の望月長之助師について長唄囃子の笛を習った。二十七歳前後であった。その後、下座音楽によく出ていた深川の千葉氏に囃子の笛も習う。同じ門に今の若山胤雄氏の顔もあったという。この千葉氏に笛を習ったのがきっかで囃子に入るのだが、囃子の太鼓を知らなかったので、千葉氏の勤めにより長谷川金太郎の元に太鼓を習いに来たのである。これ以後、長谷川金太郎社中の笛ふきとして長く活躍するのである。
神楽・長唄の要素が入ったその音色、節まわしは、一般の囃子の笛とは幾分違った品の良さを持ち、それが神田囃子の雰囲気によく合ったとされている。
吉村のカッコは、その持ち味を充分生かして実にすばらしいものであったと言う。又、その姿勢も美しかった。
戦後、五反田の高井清一、鼓友会の小林信吉、清水康則など現在の長老たちは、この吉村から笛を習った。特に小林信吉は、神楽も習い両方で活躍している。
吉村長吉は、長く神田囃子の立笛として神楽の笛方として活躍したが、本職の神楽師とはならず、東京電力に勤め続け定年で退職された。現在も元気でいられるが、一時体を悪くされてから神楽・囃子からは離れている。
以上が、戦前の神田囃子の主な事柄、人物の概略である。その他にも折々に新しい人が金太郎社中に加わっている。四助の杉田さんと言われた杉田浩司郎、松永寅次郎、小池彦二郎などの人々である。小池は獅子の舞手であったが、その師は前述の鈴木金次郎ではない様で、誰から習ったか分らない。近藤三郎、現青山会長は小池から獅子を習っている。小池は、獅子の稽古にはかなり努力し、工夫をしていたそうで、その獅子舞は生き生きとして一つ一つの動きに、はっとさせるような美しさがあり、実にすばらしいものだったと聞いている。
時代は、やがて戦争の時代へと入っていき、金太郎社中の活動も中断を余儀なくさせられる。
(二) 戦後の保存会
(イ) 祭りの復活
第二次世界大戦は、日本の国土、人々に大きな傷痕を残した。特に私達の故郷である東京は数度に亘る空襲により、人命・建造物をはじめ、伝来の貴重な宝物・家財等の多くの有形、無形のものを失った。
しかし、終戦を迎え疎開者も戻り始め、復員者も増えるにつれて、急速に復興していった。昭和二十二、三年頃になると最も被害の大きかった下町でも、人々は漸く心の落ち着きを取り戻し、町内会の様な団体もその活動に於て、戦時中にはない余裕を持てる様になった。その様な中で各所の神社では、戦後初の例大祭――特に復興祭と呼ばれた――が行われた。神田でも昭和二十三年に大々的に執り行われた。
(ロ) 保存会の情況
長谷川金太郎社中は、戦争の激化と共にほとんどその活動を中断せざるを得なくなっていたが、終戦後間もない昭和二十三年に、大黒柱、長谷川金太郎を失ってしまった。祭礼も復活され社中はその活動の場を取り戻すのであるが、その出鼻をくじかれた様な非痛な出来事であった。その当時、二代目金太郎の直接の薫陶を長く受けた中心メンバーは青山啓之助をはじめ、鈴木金次郎、鈴木忠治、田代源吉、大田庄之助、吉村長吉、竹内和吉の子信治等、その数は決して多くなかった。金太郎亡き後、保存会は金太郎社中の大番頭的存在であった青山啓之助の下に徐々にその活動を拡げていくのである。
(ハ) 鼓 友 会
現在保存会にある太鼓の中の一組に『鼓友会』の銘の入ったものがある。この鼓友会の人々は、戦後に於る青山啓之助の最初の弟子である。
戦後の混乱もようやく静まった昭和二十五年、今の上野五丁目町内に時々旅行に行ったり一緒に遊んだりする趣味の会の集まりがあった。その中から誰言うとなく何か稽古事を始めようという声が上った。長唄、清元、日本舞踊等、江戸以来盛んな芸事は多数あるのだが、この様なものはとかく物入りも多く適当でない。何か良い事はないかと考えた末、お囃子が一番いいのではないかと言う事になった。しかし、長唄、踊りのお師匠さんは多いのだが囃子などというものは、一体どこで誰が教えてくれるものか見当もつかない。困っていたがメンバーの一人永島徳治の弟の手蔓で逗子に疎開している良い師匠がいることが分った。そこでメンバーの中でも年長の福田優吉、清水康則ら二、三人の人が逗子に挨拶に行き、正式に教授を受ける事を約束して来た。この逗子の師匠が、青山啓之助である。
今、上野のステーションホテルのある所に無極亭という貸席があった。そこを稽古場として毎週二回集り、稽古が始められた。太鼓がなかったので古畳を使って稽古をした。当初は、青山啓之助一人で教えていたが、締太鼓の口伝も一通り仕上げた頃から笛の吉村なども来て笛入りの稽古を始めた。約二年近くの稽古を積み、かなり上達した時に彼らは、より楽しくより良い本格的な稽古が出来るように太鼓を一組新調した。グループの名を『鼓友会』と決め大胴の胴に記念の為に年月会名、個人名を刻み込んだ。
鼓友会
昭和二十七年十月吉日
堀内秀男 山田徳治郎 永島徳治 山田 脩
江波戸良一 小林信吉 福田優吉 手島本男
清水康則
囃子を習った人ならば誰でも経験するのだが、囃子の面白さがはじめて分る時というのは口伝を仕上げ、笛に合わせて太鼓を打てる様になった時である。いわば運転免許をとって、横に教官もなく自由に車をあやつれる様になった見たいなものである。鼓友会の人にとって、太鼓を新調した頃が丁度その時期だった。後に述べるが、保存会としてもこの頃は、無形文化財の申請で大きく動いていた時期だった。勢い、鼓友会の活動も活発になる。個人の段階では、より高いレベルの稽古として山田脩、小林信吉、清水康則、江波戸良一の四人が立笛の吉村を招いて清水宅その他で笛の稽古を始める。また会としては近所の堀田という家の二階で、鼓友会二期生とも言うべき人々の稽古を始める。ただ残念ながら二期生の中では最近に至るまで活動した方はいない。
鼓友会は、戦後に於ける青山啓之助の一番弟子であり、その後の保存会の中核をなすグループとなった。これ以後のいくつかの稽古場で先代会長の助手として後進の指導にも活躍し、現会長となっても多くの人々を養成してきた。現在の若手会員の多くは、清水、小林両氏の指導を受けている。特に小林信吉は、立笛として多くの笛吹を育て上げ、又、最近では上野・市場・茅場町等の自らの稽古場から河田、星等の人材を育て上げ保存会の為に力を尽くしている。
(ニ) 広尾の稽古場
広尾、五反田の近辺には、青山啓之助のおとうと弟子の杉田浩司郎、松永寅次郎等の人がいたが、昭和二十四、五年頃に高井清一、近藤三郎らが集まり、松永宅へ吉村を招いて神楽の稽古をした時に神田囃子の笛の稽古も行った。昔から笛の稽古は特に難しいと言われ、笛吹の数は少なく保存会でも笛吹の確保には常に苦労していたと言う。高井、近藤は、目黒囃子を習得してはいたが、神田囃子の太鼓の手も知らないうちにいきなり笛を教わったという。しかし、この稽古は人も少なくなり、あまり続かなかったようだ。
その数年後、杉田を中心に広尾に稽古場を作り青山啓之助を招いて後進の育成をしようと言う事になった。高井、近藤はもちろん秋山健太郎、倉田、斉藤、秋山らが話を聞き伝えて集った。これが広尾の稽古場である。
杉田宅で、口伝の稽古から始めた。杉田宅には太鼓もあったので、それも使われた。青山を中心に杉田、松永、小池らが助手になり約一年程で締太鼓を一通り仕上げた。その後は、杉田宅では特に継続的な稽古は行なわれなかったらしいが、広尾神社で時々稽古をしたという。ここでは小池から近藤が獅子を習っている。近藤はその後自ら練磨工夫して『通し』も身につけた。大笑いの面をつけたそれは、見る者を思わず笑いにさそい込む、実に楽しいものだった。
この稽古場から出た高井、秋山の両氏は現在も長老として保存会の為に活躍している。
(ホ) その他の稽古場
昭和二十年代の終わりから三十年代は、日本全体が前向きに進んでいる時代だった。文化の面でも伝統的なものが見直され盛んになりつつあった。
保存会でも前記、上野、広尾の他にも囃子を志すものが増え、竹町、九段、三田などの各所に於て青山会長は、多くの弟子を養成していた。しかしながら、稽古場もそれぞれ離れ、一つにまとまっての稽古も不可能なこともあり、先代が一通り教えてしまった後は、活動も鈍り現在まで保存会に関係している人はいない。
(ヘ) 東京都無形文化財指定に向けて
戦後五、六年もたち人々の心も落着きを取り戻し、日本古来の伝統芸能・文化に再び目を向けるようになった。そこから、有形無形の文化財の保存という動きが出て来たのである。国、都、区それぞれで文化財の調査、指定、保存の行動が起った。
昭和二十六年頃、青山啓之助の東京の仕事場は大塚慶子方にあった。大塚が地域の活動に協力していた所から区の社会教育関係の職員と面識があった。彼らは初め青山が江戸以来の神田囃子を受け継いでいる事を知らなかったが、やがてその事を知ると江戸東京の伝統芸能である神田囃子に深い関心を持った。彼らと当事者である青山・大塚らの神田囃子保存に対する熱意とが一つになり、無形文化財指定への行動が始まった。千代田区役所の松沢満氏、朝戸課長、佐藤二郎氏と大塚らの精力的な活動により、多数の名士の賛助を得て昭和二十七年には無形文化財指定が確定した。そこで保存会では、協力を頂いた方等に向けて趣意書を発表した。奉書に印刷されたその文章からは、当時の関係者の喜びと意気込みが、ひしひしと伝わって来る。長くなるが貴重な文書なので以下に全文引用する。
趣 意 書
祭礼には無くてならぬものに祭礼囃子があります。神事の様式でなくて祭礼としての姿で享保年間よりこのかた著しい変遷を経て来ましたが一般大衆に深く親しまれて来たのが祭礼囃子であります、神田囃子は江戸末期に神田堅大工町屋根屋喜三郎が葛西囃子葛飾囃子等雑然としたものを江戸囃子としてその型式を整へたのに始まり、これにより初代長谷川金太郎は自から技を練る一方今日の神田囃子を纒めあげたのであります。
二代目長谷川金太郎は初代の薫陶を受け斯界の名手として巷間にもてはやされた人であり、勢ひ低俗に流れ勝ちの囃子を江戸独特の情緒とそして品位を保たせ今日まで存続させた業績は多大なものがあります。この名人二代目長谷川金太郎より直接指導をうけました私共社中一同及びその関係者は神田囃子保存会の名称のもとに斯道の為め聊か微力をつくして今日に到ったのであります。
この度東京都無形文化財保護委員会は古典芸術保存の為め我が神田囃子保存会を通じ無形文化財として神田囃子を指定し永く後世に斯の大衆芸術を残す意図を明かにされましたことは欣懐に堪えません。
終戦後特に近年東京都を始め各地方に於て急速に祭礼が復活しつゝありますが大都会に於ては社会事情がその変遷をさせずには置かず江戸情緒の何物かは忘れられ品位は失はれ低俗な見世物興行化しつゝある事は心ある人々の深く悲しむところであります。
こゝに於て我々はこの古典芸術としての神田囃子をあくまで昔の好き姿を失ふことなく保存する一方、温古知新の心に則して進取創意を凝らし、之れが普及を念願するものであります。
此の度神田囃子が無形文化財として指定をうけました機会と又同好の多くの名士の方々の賛助を得まして上記目的達成を心より願ふ私達の微意に対し一層の御高配と御声援を切望して止まない次第であります。
充分意を尽し得ませんが不取敢御挨拶申し上げます。
昭和二十七年八月
神田囃子保存会
長谷川 金太郎 社中一同
宗家代表 浅 見 鉦 吉
賛 助 員(イロハ順)(略敬称)
五笑会 伊志井 寛 春風亭 柳 橋
石 川 欣 一 和 田 保
徳 川 義 親 吉 岡 憲 司
辰 野 隆 中津川 康 之
益 田 信 義 久保田 万太郎
宮 田 重 雄 正 岡 容
獅 子 文 六 船 井 小阿彌
志 賀 直 三 近 藤 嘉 平
木 下 華 聲
石 黒 敬 七 岸 澤 式 佐
一龍齊 貞 丈 北 林 谷 榮
花 園 歌 子 宮 川 曼 魚
徳 川 夢 聲 白 根 鶏 兒
轟 夕起子 望 月 長之助
神田明神 大鳥居 吾 郎 森 晴 三
明治座 太 田 雅 充 文芸春秋 小 野 文 春
(因に浅見鉦吉は二代目長谷川金太郎の甥に當り宗家を預る者で御座います)
この様に昭和二十七年には文化財指定が確定していたはずであるが、葛西でも同様の指定を受ける動きが起り、都としてはいろいろないきさつから、両者を同時に指定する事になり、申請のおそかった葛西囃子に合わせて保存会の指定も翌年に持ち越された。
右の趣意書と時を同じくして、保存会の報告に基いた調査書が、千代田区教育委員会より都教育委員会へ提出されている。神田囃子の由来、実施の時期、実施者、器具、曲名などが簡単に紹介されている。
ここで目につくのは、実施の時期で『二月の初午の日を皮切りに神事に寿ある祭礼等に随時』行なわれたとある。正月の奉納は昔はなかったようである。又、当時の会員が約三十名だったことも分る。
二十七年には以上の様な事が行なわれたが、前記の事情で指定が一年おくれた為に、指定に関係する公式な動きは翌年に持ち越された。
(ト) 無形文化財指定
昭和二十八年、正式に無形文化財に指定される時が近づき、秋頃からいろいろな活動が活発になった。
当時の保存会は創立期メンバーのなかの、竹内和吉、波田睦六、岸平治郎、加世清蔵などの人々は亡くなっており、青山啓之助を中心に田代源吾、鈴木金次郎、竹内信治、鈴木忠治、杉田浩司郎等が主だったメンバーであった。この人々と大塚は、区役所の職員と連絡を密にし、区役所の要請もあって、デモンストレーションの意味も含めて、数々の公式の場に出演する。
九月十七日には神田須田町の大塚方に区職員及び、鈴木金次郎、太田、竹内、志賀直三、青山啓之助、杉田、田代、大塚らが集り、『保存に関する懇談会』を開いた。この場で、保存会の規約、後援会の設立、指定に関連する行事への出演等が相談された。
九月二十四日には、今の東京電機大学の所にあった千代田区役所〔元神田区役所庁舎〕の三階の公会堂に於て、来たる十月二日に催される都郷土芸能大会へ向けての稽古が行なわれる。前年の昭和二十七年に東京都は、十月一日を『都民の日』と定めた。その日に都は数々の催し物を行うことにしたのだが、その一つに『東京都郷土芸能大会』というものを加えた。これは、東京都の各地に伝わる郷土芸能を毎年いくつかづつ集めて、広く都民に紹介し、自らの郷土に対する関心を深める目的で行なわれるものである。二十七年に第一回が開催されたが、第一回という性質上、ダイジェスト的に多くの芸能が披露された。昭和二十八年の第二回には方針を変え、出演の団体を減らし一つ一つの芸能を充分に鑑賞できるようにした。この第二回に神田囃子は、千代田区代表として出場する事になっていた。祭り囃子としては、東京都で初の無形文化財に指定が決まっていた神田囃子が、お披露目の意味もあり、特に選ばれたのだと思う。
第二回都郷土芸能大会は、昭和二十八年十月二日、日比谷公会堂で催された。神田囃子の他に伊豆諸島、八王子等の芸能グループが、五・六団体ほど出演した。神田囃子の演目は素囃子と寿獅子であった。参加者は、鈴木忠治、太田、竹内、志賀、青山啓之助、杉田、吉村である。小池が獅子を舞った。
これとは別に、前日の十月一日には、大塚方に於て文化放送による囃子の録音も行われた。解説をまじえながらの演奏であった。鈴木忠治、竹内、志賀、杉田、吉村、青山啓之助が参加した。
保存会が正式に無形文化財に指定されたのは、文化の日の十一月三日であるが、十月三十日に、保存会は披露目式を行なった。区役所〔現在の電機大学の所〕三階の公会堂において区関係者、後援会、保存会会員等、多数の人々を集めて盛大に行なわれた。ここにおいて、長谷川金太郎社中―東京都無形文化財、神田囃子保存会がスタートしたのである。初代会長には、金太郎社中の重鎮、青山啓之助が就任した。又、金太郎の甥の浅見鉦吉が宗家代表として参加した。
笛 ……………………………… 吉村長吉
締太鼓 ……………………………… 鈴木忠治、小池彦三郎 (写真1)
大 胴 ……………………………… 青山啓之助
鉦 ……………………………… 杉田浩司郎
による記念演奏と小池彦三郎による寿獅子も賑やかに行なわれた。
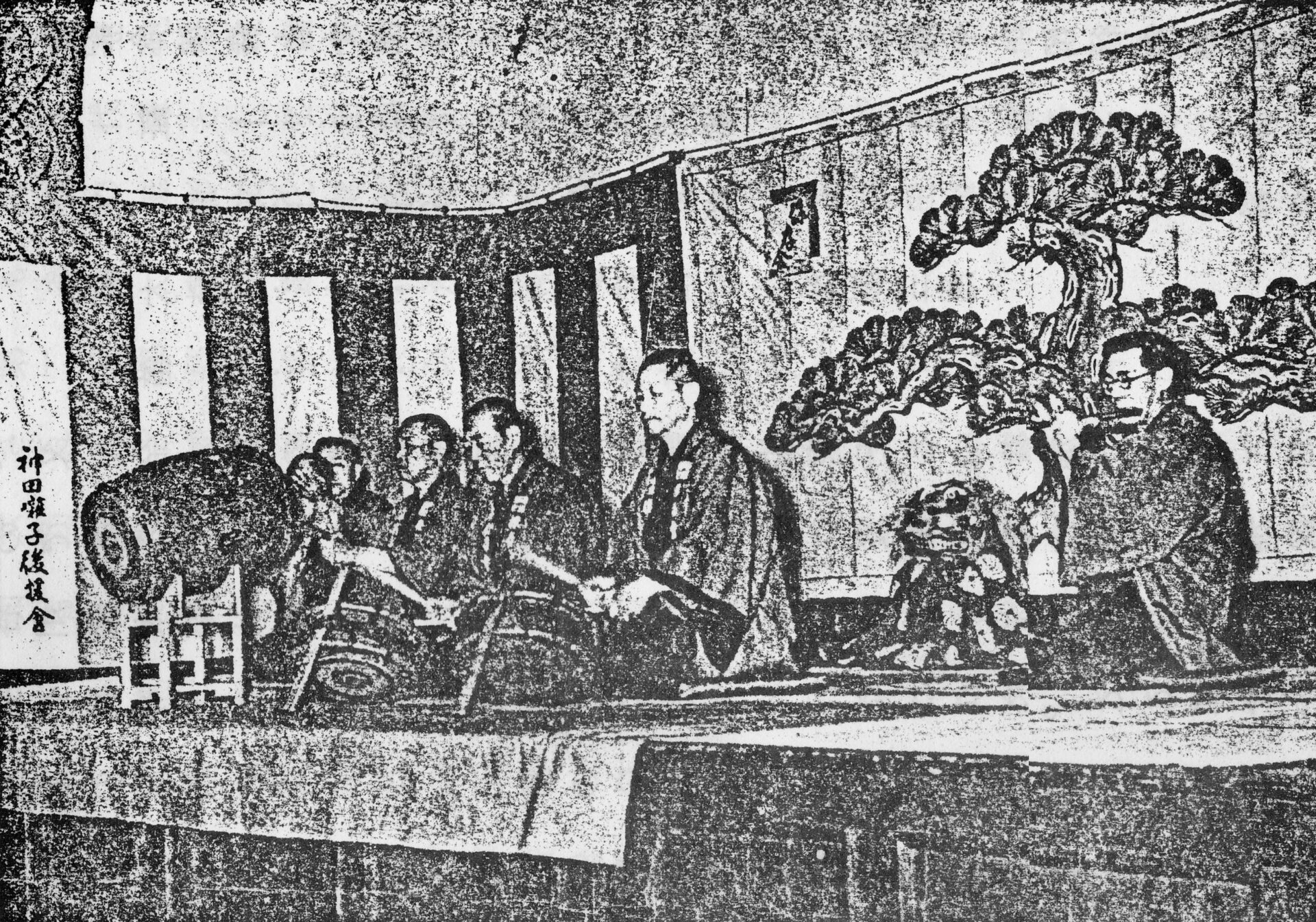
写真1
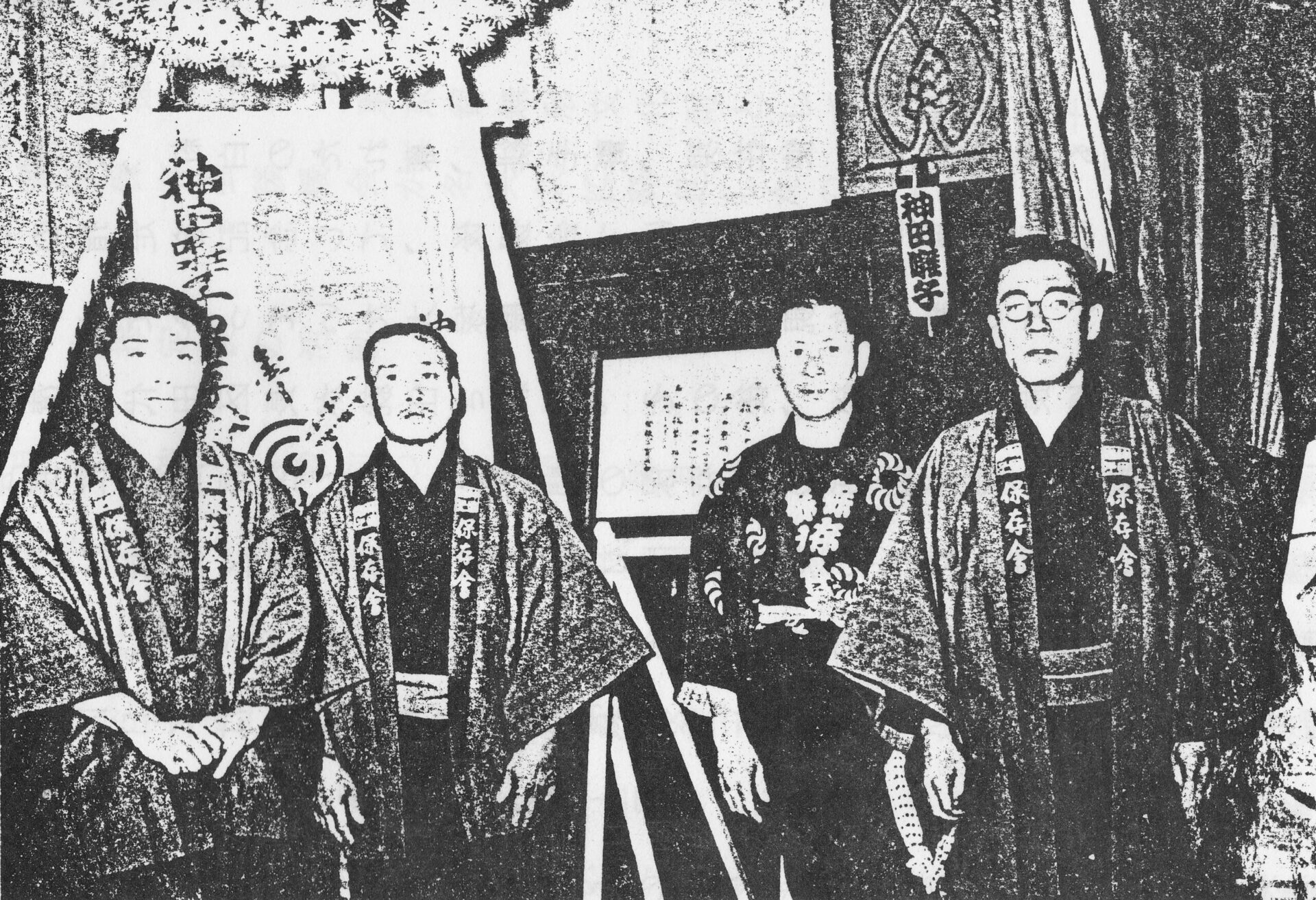
青山栄二郎 青山啓之助 小池彦三郎 吉村長吉
この頃には、保存会の活動を支える後援会の設立も『後援会設立発起人』代表の市村駒之助、大塚らの手によって急がれていた。実質的にはもう動いてはいたのだが。
十一月四日には、区役所三階議員控室に於て、設立準備委員会が開かれている。ここで後援会規約などが審議決定されている。初代後援会会長には林慶之助氏〔神田の鋼材問屋社長〕が就かれ、規約による名誉会長には区長として、この間の保存会の活動を強く後援して頂いた村瀬清千代田区長が就任された。その後、後援会会長には実質的に活動の中心になっていた大塚慶子が就任し現在に到っている。
この指定を記念して、後援会では三十日のお披露目の時、つむぎの茶の伴天、紅白のたれ幕、緋毛氈、現在使っている最も良い太鼓一組を保存会に寄贈した。
以上の様にして、東京都無形文化財としての神田囃子保存会並びに神田囃子保存会後援会が名実共に発足したのである。
(チ) 指定後の活動
正月の奉納――戦前の一時期、毎月一日、十五日に神田明神へ囃子の奉納を行なっていた事があるが、日中戦争の激化等によって中断されてしまった。その後この様な形での奉納は行なわれなかった。指定後初めての昭和二十九年正月から、今でも恒例となっている正月の奉納が始まった。一回目から、五十三年の正月までは一月一日午前零時より日の出までの間、奉納していた。五十四年からは元日午前零時より夕方まで、二日三日は朝から夕方までの三日間奉納している。素囃子はもちろん、獅子、通しも出て賑やかに行なわれている。区囃子教室からの会員の増加により、三日間盛大に行う事も出来るようになったのだが、初詣で客からも正月気分を盛り上げるものとして喜ばれている。
舞台での活動――文化財指定に伴い、その前後には区役所を通して公けの場での発表の機会が多かった。先に記した都郷土芸能大会、文化放送の録音などもそうである。
昭和二十九年五月三十日には『伝統芸術の会』主催による”神田囃子をきく会”が催された。一ッ橋の如水会館二階日本間で行なわれた。
素囃子の出演者は、笛―吉村、調べ―鈴木(忠)・小池、大胴―青山(啓)、鉦―竹内で杉田の解説が入った。寿獅子は、獅子―小池、笛―吉村、桶胴―鈴木(忠)、太鼓―青山と当時の記録に残っている。ここで気になるのは、寿獅子で、鉦の出演者が記されておらず、又、四ッと言って、締太鼓に桶胴をつけて打つのが、太鼓として別に一人加えられている事だ。投げ合いでも入って、四ツの他に太鼓を加えたのか、記録違いなのか、調査不充分の為明らかに出来ない。
この日の出演者もそうであるが、この頃の会への出演者を見ると笛の吉村、太鼓の鈴木(忠)、大胴の青山(啓)、獅子の小池等と呼ばれて今に言い伝わる名人上手といわれる人々が常に中心になっている。保存会自体、人員が減少し、後継者の養成に力を入れていた時期であったが、質的には真に無形文化財に指定されるべき高い水準にあったことがしのばれる。
『神田囃子をきく会』のプログラムは、はじめに一ッ橋大学教授による伝統芸能と祗園囃子についての講演があり、神田囃子の演奏と解説、獅子舞、テープによる祗園囃子の鑑賞、最後に質疑応答となっている。出席者は多くはなかった様だが、大学関係者などかなり教養の高い人々だったらしい。プログラムを見ても分るように、単なる鑑賞会に終わらせるのではなく、神田囃子に対し西の伝統的祭り囃子である祗園囃子を出し、東西の伝統的二大祭り囃子を対比させながら、かなりアカデミックに取り上げられた様である。
元来、庶民の芸能である囃子などを、アカデミックに取り上げたからといって、その事自体特にすばらしい事であると言う訳ではないが、戦争により一時中断を余儀なくされていた伝統的な文化、芸能などを漸く取り戻し、更に後世に伝えていこうとしていた当時の人々の喜びや意気込みがこの様な会を開かせたのだと思う。その真摯な態度、精神は今の我々にとっても重要な事であると思う。現在では、テレビなどを通じて伝統芸能に接する機会も数多い。見る方も演ずる方も単に娯楽的な方向ばかり追い求め、ショー的な要素ばかり強くなっていく様であるが、三十年程前にこの様な会が持たれていた事は、確かに注目に値する事である。
第八回全国リクリエーション大会――昭和二十九年八月五日、六日の二日間、仙台市において第八回全国リクリエーション大会が行なわれた。神田囃子は『郷土芸能文化財の部』に参加した。会場は、仙台市公会堂とレジャーセンターがあてられていた。保存会からは青山(啓)、杉田、松永、小池、吉村、青山栄二郎が参加した。
以上、文化財指定前後の保存会の主な活動を紹介してきた。
(リ) 千代田区囃子教室
保存会は、常に後継者の育成には力をそそいで来た。鼓友会、広尾の稽古場からも、文化財指定後に新人がその活動に参加して来たのであるが、芸事の常として、人の出入りはいつも激しく、後継者の育成もここまでやれば充分という所がない。又、千代田区にある唯一の無形文化財として、広く区民にも参加の機会を提供する為に囃子教室が行なわれることになった。昭和三十一年三月に千代田区、区教育委員会、神田囃子保存会は、三者連名の生徒募集要項を配布した。『千代田区唯一の郷土芸術たる神田囃子は、先年都無形文化財に指定されているが、後継者育成の為に囃子教室を開くことになった』旨の案内が冒頭に書かれている。この中で面白いのは対象者として、個人も可だが『一町会五人〔一組〕が望ましい』と書き加えられている事だ。これは、祭りの時に実際の役に立つ理想的な人員構成を目論での事だと思うが、随分欲張ったものだと思う。実際に集まったのは個人が多かったと思われる。
期間は、四月から八月までで毎週二回、火曜日に万世橋区民館、金曜日に番町区民館、指導は保存会幹部、会費は月百円となっている。
六十二名の人々が参加し、出席率はかなり高い。当時の出席表、会員証等が区に保存されている。二十名の人が名前と共に囃子教室修了者として記録されている。その他に十二名優良者という人もいたらしい。
この教室には、青山会長を中心に鼓友会や広尾で育った新人の清水、福田、高井、近藤等が、助手として指導に当った。はからずも、この囃子教室はこれら戦後保存会の第一代とも言うべき人々が、以後の保存存会の中堅たるべく後進の指導を経験する良い機会にもなったのである。
千代田区の協力を得ての囃子教室の開催は、この四ケ月間の一回を以て終了する。おそらく予期以上の好成績で二回目三回目を募集しても人数ばかり増え、一人一人の充分な稽古が望めなくなるのを懸念した為であろう。
教室は終了したが、万世橋区民館での稽古はこれ以後も続けられた。これまでは、上野・広尾・九段などそれぞれに分散した稽古場しかなく、出演の機会がなければ相互に交流する事も比較的少なかった。しかし、ここに於てはじめて保存会は万世橋区民館という社中統合の稽古場を持つ事が出来たのである。この事は、古い形の師匠の出稽古による社中ではなく、新しい組織として保存会が発展する土台が整ったといえる。師匠との縦のつながりだけの社中ではなく、一つのグループとして、常に一緒に稽古し行動できるというのは、構成員各個の親睦、芸の練磨にとって、欠く事の出来ない事であると思う。これ以後、稽古場は移るが、保存会は常に一ケ所の稽古場に参集して稽古を続けている。
(リ) 音 の 記 録
今では、ビデオも普及し、映像までも簡単に記録できるようになった。テープ、レコードも、自分たちが接することができない、場所、時間の演奏を耳にすることが出来る。
保存会でも、古くは、二代目金太郎の演奏がSP盤で残っているし、その他、折々にレコードなどに録音されている。
昭和三十七年十月、ビクターレコードの第十七回芸術祭参加作品『江戸の神楽と祭囃子』の中で素囃子の演奏を録音した。笛―上野光之、調べ―小池・松永、大胴―青山(啓)、鉦―杉田の演奏者であった。
同じメンバーで、カッ子入り囃子と投合もレコードになっている。これらによって、大胴の名人と言われた先代会長の演奏を聞く事が出来る。
その他に、笛―吉村、調べ―鈴木(忠)、小林(信)、大胴―竹内、鉦―矢沢というメンバーでのレコードもキングから出ている。
時は後になるが、昭和五十年にも、小林(信)、清水、秋山、小林(征)、立野、藤原による東芝EMIの録音があるが、レコードには、わずか二分間程しか集録されていない。
レコードとしては出ていないが、東京文化会館の資料として、清水、近藤、秋山らによる録音も行われている。
(ル) 現会長の就任――昭和四十年
三十一年以来、万世橋区民館での稽古は続けられていた。この間、資料的に乏しいのでどのような活動があったか、残念ながらはっきりしない。
この年の一月四日、二代目長谷川金太郎から神田囃子を受け継ぎ、昭和二年に保存会が作られて以来、特に無形文化財に指定されてからは、無形文化財神田囃子保存会の初代会長として、半世紀近くに亘って神田囃子の為に活動して来た青山啓之助師が亡くなった。自ら囃子の演奏も行い、その上保存会という組織を運営し、後進の育成にも力をそそいできたリーダーの死は、保存会にとって大きな傷手であった。その頃は既に金太郎の直弟子で昭和初期に活躍した人々は居らず、保存会の中堅は、戦後に啓之助が育てた人々であった。上野、広尾からの人々、万世橋で新たに育った人々は、師匠である啓之助のもとに一つにまとまっていたのであるが、この中から彼にかわりうる指導力を持つ人は生まれていなかった。しかし無形文化財としての保存会にとって、次の代表者を選ぶ事は至急の課題であった。
翌二月に納骨を終え、追善の法要を営んだ後、保存会会員は、須田町の料亭牡丹に集った。早速、次期会長の人選について話し合いが始められた。数人の人が候補と目されていたようだが、なかなか話はまとまらない。話が混乱する中で、啓之助の次男栄二郎はしばらく会場をぬけ出した。栄二郎は、物心着いた頃から、囃子の音の中で育って来たが、あまりにも囃子が、人を祭りのとりこにしてしまうのを長く見てきて、今一つ囃子にとび込むのをためらっており、当時まだ太鼓は習っていなかったと言う。とは言え、蛙の子は蛙、小池からは、獅子を習っていて、昭和二十九年の仙台のリクリエーション大会をはじめ、早くから各所に獅子の舞手として出演しており、又、各所に出演する時の世話役としても、以前から保存会の為に力をつくして来ていた。その栄二郎が会場を出てしばらくすると、突然会場から大きな拍手がわき起った。急いで戻り、訳が分らないながら恐らく会長が決まったのだと思いながら一緒に拍手をしていた。拍手がおさまり、話を聞くと、何と自分が次期会長に選ばれた事を知り驚いてしまったそうだ。彼は、自分は適任ではないとして、はじめから辞退していたのであるが、囃子や会の運営について、雑多の主張を持つ人達をまとめていく事を考えれば、栄二郎のそれまでの会に対する働き、運営に対する責任ある取り組みを認めない会員はいなかった。当時、栄二郎を置いて他には適任者は、はじめから居なかったと言える。この様にして昭和四十年二月、現保存会会長、青山栄二郎が誕生した。
(ヲ) ハービーマンとの共演
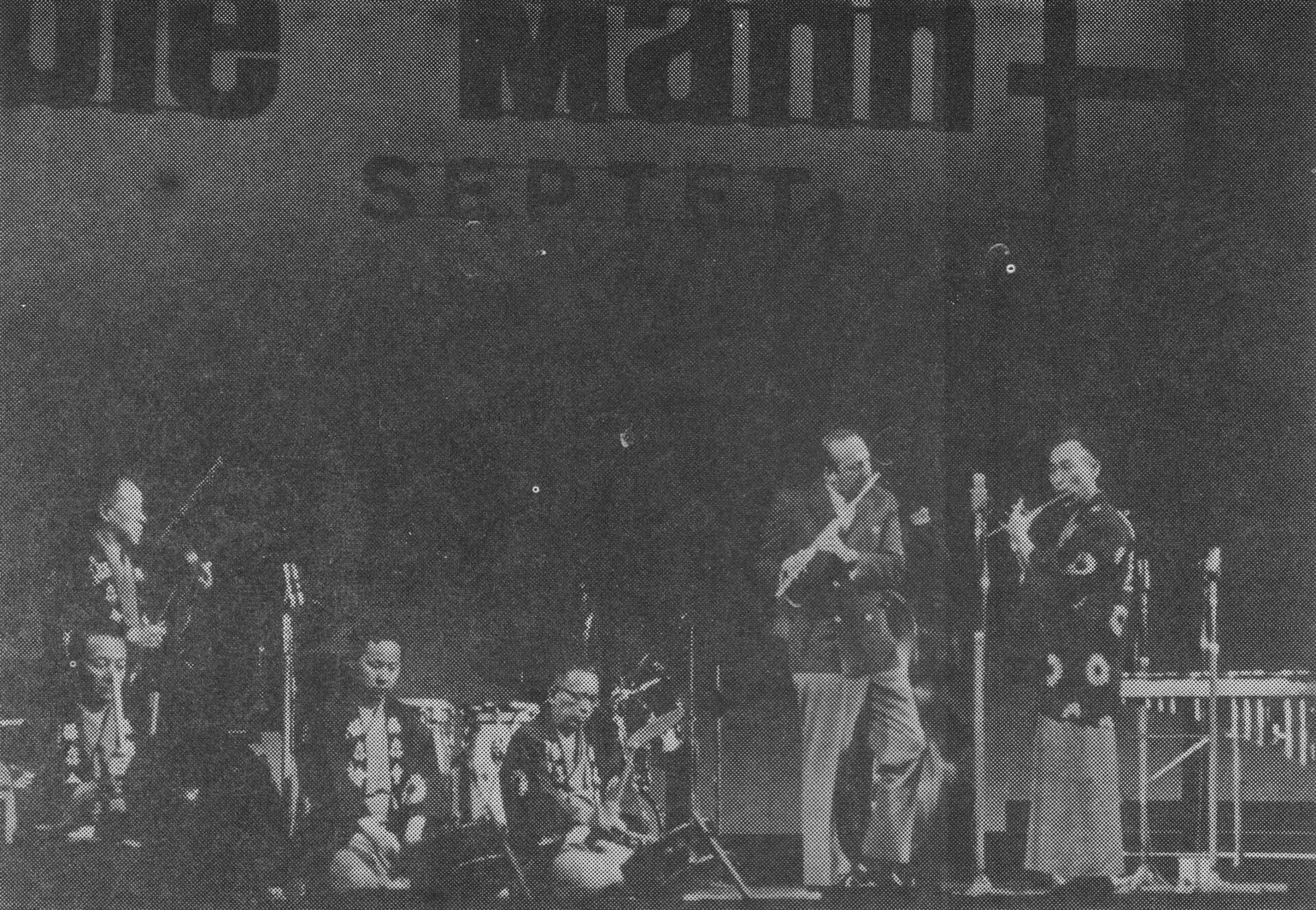
昭和四十一年六月十四日東京厚生年金ホールに於て、来日中のジャズミュージシャン、ハービーマン達との共演が行われた。出演は、笛―黒崎、太鼓―秋山(健)・秋山、大胴―倉田、鉦―杉田であった。演奏は囃子方により『投合』がしばらく演じられて、その間にハービーマンらは、笛の曲をつかみ、サクスホン、フルート、トランペット等が、それぞれ交替で笛の代わりに囃子に加わってくるという形で行なわれた。共演とはいっても、その方法は単純なものであったが、現在の様に邦楽の分野での洋楽との融合という様な試みが盛んになる以前の新しい試みであり、又、広い意味での庶民のバイタリテイーの音楽的具現とも言えるジヤズと囃子の結び付きは、非常に興味深い出来事として好評を博した。この企画は、ラジオでも再演されている。この時参加した囃子の方々の思い出話しを聞いても、真先にこの話しが出てくる位、印象の強い出来事であった様だ。
(ワ) 稽古場の移動
昭和三十一年の囃子教室以来、四十三年初夏に建て替えの為に使えなくなるまで、十二年間、万世橋区民館の二階日本間での稽古がつづけられた。
囃子教室以来、多数の人に一時に教える機会もなく入会する人、来なくなる人、会員の顔ぶれも中堅を除いて常にかわっていた。ハービーマンの後、会の運営上の問題、囃子に対する意見の相違などから、砂をけたてるように脱会して行く者も一部にはあった。この間、清水、福田、秋山(健)等は、ずっと会の為に力を尽し後進の指導等に当っていた。また、四十年頃には現在幹事長として若手の中心に立ち、会長を補佐し、会の運営に重きをなしている小林征治が入会している。
区民館が使えなくなり稽古場が移らなければならなくなった時、神田神社の好意により神楽殿を稽古場として提供してもらえる事になった。神田明神は、氏神であり神田囃子にとっては、最高の晴れ舞台である神田祭りの御祭神であり深いつながりのある神社である。ここに、現在から未来に至るまで稽古の中心を持つ事が出来たのは、保存会にとって最も幸せな事であった。
昭和五十三年以前、神田神社がはとバスのコースになる前は、神楽殿は普段、雨戸がしめてあり稽古はその中で行った。松羽目を背に先生方が、しかつめらしい顔で並び、表側、雨戸を背に生徒達が並んだ。神門側に社殿向きに太鼓を並べて稽古をした。昭和四十六年秋に、立野喜久雄、藤原健史、神田 茂 等が入会したが、この頃は会員数が少なく、比較的高齢である先生方と二十代の彼らの間の世代がぬけていて、保存会は苦しい状態であった。稽古はというと一回囃子が終ると三十分、時には一時間も昔の事やその他の囃子の話などをして、のんびりとはしていたが、囃子を演じている間は、間違えると咜責されたり、何度も繰り返されたり、姿勢や行儀の事まで細かく注意され、かなり厳しかった。先輩、後輩とも保存会の危うい現状を無意識のうちにも感じ、そこから脱けだす努力をしていたのである。
(カ) 鞆 絵 組
昭和四十六年の新人中、立野、藤原、神田の三人は初期の稽古を終え青山会長一人だった獅子舞も習い覚えた。歳も近く仲も良かった彼らは、会長の言い付けにより三人で組を作った。これが鞆絵〔ともえ〕組である。また彼らは、四十八年七月、獅子舞を習得した記念に白壇の獅子頭をつくり、会に寄贈した。
鞆絵に遅れる事数年で池谷祥子、その少し後に、川北久一が入会する。川北は後に鞆絵の一員ともなった。この後、千代田区囃子教室からの新人が入会するまでの最も人的に欠乏していた時期に、これらの人々は、小林(征)を中心に保存会の若い力として活躍し、又、囃子教室からの人々のよき先達ともなった。
(ヨ) 三越東都のれん老舗の会
毎年三月に恒例として出演している、のれん会に神田囃子が参加したのは、昭和四十五年からである。この年は、東都のれん会結成二十周年にあたり、記念として会場の一部に特設舞台を設け、芸妓の舞踊と囃子が出演した。これが好評でそれ以後、毎年続いている。保存会にとってこの会は、若手のよい勉強の場となっている。
(タ) 伊勢神宮遷宮式
昭和四十七年は伊勢神宮の遷宮の年であった。神田囃子は、東京都より選ばれて、関東地区代表として、遷宮式での郷土芸能の奉納に赴いた。十月十五日には特に選ばれて、内宮の神楽殿に於て、囃子と獅子の奉納をした。非常にりっぱな所であり、申し分のない晴舞台だったそうだ。この日は、他に近辺の学校でも土地の人の為の会が催され、各地の芸能と共に神田囃子も披露された。翌十六日には、神宮会館に於て、参加各団体がすべて集り、発表があった。ここで神田囃子は、さすが東京の代表、実にすばらしいと絶賛を受けたという事である。
この時の参加者は、青山、小林、高井、清水、秋山、近藤、松永であった。

近藤三郎 松永寅次郎 秋山健太郎 清水康則 小林信吉
(レ) 国立劇場出演
第三十一回民俗芸能公演、日本の太鼓に保存会は出演した。毎年、国立大劇場に於て、太鼓を中心テーマとした芸能の公演が開かれているが、昭和五十四年は『太鼓の祭囃子』というテーマで特に東京、大阪、京都の三大都市の祭囃子を中心として、九月十五日、十六日に開催された。神田囃子、天神祭のだんじり囃子、祗園囃子である。その他、大島御神火太鼓、沖縄の屋慶名エイサー等も参加し、神興も繰り出されて華やかに催された。
十五日、笛―小林(信)、調ベ―秋山・立野、大胴―池谷、鉦―神田。十六日、笛―小林(信)、調ベ―立野・川北、大胴―小林(征)、鉦―秋山であった。出演者は小林、秋山両先生の他はすべて昭和四十年以後の若手会員によって構成された。つまり、現会長の弟子の世代が初めて大きい舞台へと出られるまでに成長した事をあらわす、記念すべき出来事であった。
(ソ) 千代田区囃子教室
昭和五十一年頃、都教育会館に各区の社会教育関係の職員が集まり、その席で品川の神楽師の間宮氏と保存会の青山会長が講演を行った。その中で会長は、千代田区の人口減少等による後継者不足を訴えた。当時保存会では、鞆絵など若手が育ちつつあるとはいえ、やっと二組の囃子が同時に出来る程の人数しかいなかった。幸いその席に千代田区職員の岡部氏が出席しており、区の唯一の無形文化財である保存会に、極力、協力することを約束してくださった。それが遂に昭和五十三年に実現し、区の主催による囃子教室が生まれた。期間を一年として三年間、三期まで続き会の都合から一年の間を置いて、今年五十七年は、第四期生が稽古を受けている。前三回は会長、小林(信)等、諸先生方に鞆絵等が助手として加わり指導に当った。
一期では、二十代の若い人々が多数保存会に加わり、驚威的な速さで、笛、太鼓を習得した。二期三期からも多数の人々が保存会に入会した。
この囃子教室は、囃子をやりたいと思いながら習う機会を持てなかった者を多数発堀し、優秀で素質あるものを短期間に多数得ることが出来た。全く予期しなかった成果であり、保存会にとって非常に価値ある事であった。
第四期は、若手によって指導しているが、小林(征)、鞆絵組、池谷祥子
に加え、星一郎、一期から神保八起、深沢幹男、高橋安次、堀江剛、野島弘、三期から柘植伸一が助手として加わる程に成長して来ている。
囃子教室の生徒の中では、野島、田口久美子、柘植が鞆絵の指導で獅子舞も習得している。
近藤の指導で立野、池谷、藤原、神田は通しを半ば習得していたが、五十六年の夏、立野の母、坂東三之喜久師の所で、新たに立野、藤原、堀江、野島、田口が、おかめと、もどきの所作を習った。これはまだ稽古の段階ではあるが、より稽古し、保存会の持ち芸を増すべく努めている。
記念式典に向けて
現在、多くの会員が集まって稽古に励んでいるが、今の様な隆盛は保存会はじまって以来の事だと思う。この間、神田神社からも白壇の獅子頭の寄贈をはじめ多くの援助を賜った。神田神社というすばらしい稽古場において、のびのびと稽古が出来るのは非常に有難い事である。こうした活気ある雰囲気の中で保存会設立五十五周年、無形文化財指定三十周年の記念式が計画され、実行委員会が組織された。先輩達から受け継がれて来た神田囃子をもう一度見直し、これからの我々の糧にするためにそれぞれの分担において活発に活動を進めている。
現在の若手会員は、青山現会長のもとに明神様の稽古場で、いわば一つ釜の飯を食って育ってきた仲間であり、まとまりも強い。囃子に対する意欲も旺盛である。今後、四期生をはじめ、新しい人も数多く入会してくるのであろうが、記念式典を好機として、ますます活動を盛り上げ、発展して行くことになるのであろう。
---------- 終 ----------
本サイトの掲載内容(画像、文章等)の一部及び全てについて、無断で複製、転載、転用、改変等の二次利用を固く禁じます。