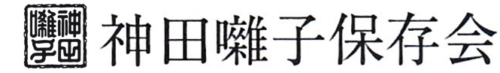第一章 神田神社の沿革
(一) 草創の説話
(二) 平将門と神田明神
(三) 神田神社の再興
(四) 康入府以後
(五) 明治期から現代
第一章 神田神社の沿革
(一) 草創の説話
創建について又その名の由来については諸説がある。
天平二年〔七三〇年〕、武蔵国の国造(くにのみゃっこ)〔当時の地方長官〕であった真神田臣(まかんだのおみ)が、豊島郡芝崎村の地に社(やしろ)を建て、地祗(くにつかみ)〔国神〕大己貴命(おおなむちのみこと)を祀ったとされ、この社のことを真神田の社といっていたのが、後に、これを略して神田神社というようになったという説。
その二は、忌部(いんべ)族〔海部族〕が、今の房総半島に定住していたが、その人々の守護神、つまりは海神として安房神社に祀られていた神を、八世紀の始めごろ分社して、豊島郡芝崎村の地に祀ったのが起源という説。
また、天平二年〔七三〇年〕、豊島郡芝崎村の神田台〔江戸城神田橋御門内、現在の大手町〕にその地の人々によって、産土の神・鎮守の神が祀られ、神田(しんでん)の神社と呼ばれた。祭神は大己貴命であった。その名の由来は、その地が伊勢神宮の神田(みとしろ)であったことにちなんでいるという説。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
神田とは、国家の公田をその神社に賃貸した地子田のことをいい、厳密には社領でなかったのであるが、それが後には社領として恒常化したのである。神田は御戸代田とも、神戸田地(かんべでんち)ともいわれて、神田の民又は、近傍の民をして耕作させた。神社は大体二割を田租とした。これを神税ともいった。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
このように、八世紀ごろ創建され、近郷の人々の産土の神・鎮守の神として崇められた。また、祭神の大己貴命は、古事記によれば『海を光して依り来神(きたるかみ)』とある。遷座の地形からみて海の守護神としても崇められたことであろう。祭礼も旧暦九月十五日に、天下太平・五穀豊穰又、豊漁や海路の安全を願う秋祭りとして盛大に行われていたという。
(二) 平将門と神田明神
神田明神は、平将門公を祀る神社としての方が有名である。各時代の文書にも『神田明神は平将門公を祀る神社なり』とあるように将門公は主神と思われているのである。
平将門は、承平五年〔九三五年〕堕落し荒廃する京都政権をしり目に、東国の民及びその当時胎動しはじめた兵達(もののふ)に支えられて、いわゆる独立戦争的な戦いを起こした。
その当時すでに坂東平野は、水運の便も開け、生産力も大きく、有数の馬の産地であり、その土地に合った独自の文化をもっていたのである。こうした東国は、京都の貴族政権にとっては、ただ遠い国、『あずまえびす』の地であり、植民地として蔑視し、搾取の対象としての地としか考えられていなかった。京都で数年を過したといわれる将門は、貴族達の何か欠落した生活、又律令体制の裏面のいやな事を数多く見たに違いない。将門には我慢のならなかったことであったろう。
『天慶の乱』の蜂起は、わずか五年間という短い期間ではあったが、平将門のことは東国の民の目に武士(もののふ)の目にその心の中に、強く深く静かに記憶され、かの地の隅々にまで伝わって行くのである。将門は、皇位をねらった逆臣という汚名をきせられたまま、俵藤太によって討たれるのである。時に天慶三年〔九四〇年〕二月十四日のことであった。首級は、京都の東の市において晒されるのであるが、何人(なんびと)かによって持ち去られ、豊島郡芝崎村・神田の社の境内に手厚く祀られて、慰霊されることになるのである。これが有名な『首塚〔将門塚〕』である。将門についての話は、これで終りにならず、その死後、いわゆる『将門伝説』・『将門信仰』として残っていくのである。
現在、将門ゆかりの場所は東京の都心部だけ取り上げてみても五ケ所とは下らない。まして将門の本拠地であった、常陸・下総はもちろん東国〔関東地方一円〕には、そのゆかりの場所が、それこそ無数にある。そればかりか日本全国二十三都府県にも及んでいるのである。
江戸・東京に伝わる伝説では、将門の首は京都で晒されるが、ある夜、白く光を放って自ら、東の方に飛び去り、武蔵国豊島郡芝崎村の地に落ちた。その音は物凄く、東国一円に轟き渡り、大地は、三日三晩鳴動し続けた。郷の人々は、恐れ慄き、近くの池で首を洗い、塚を築いて手厚く祀り、供養したので、その祟りが鎮まったと言われている。
天変地異が続いた時、それを一人の人間の祟りと考え、その人間を祀る事で、それを鎮めようとする事が、古くはしばしば行われた。菅公、将門がそれである。この場合、その人々は、決して生前悪人だったのではなく、逆に民衆には、良い人間だったと記憶され、それが不運の中に死んでいったのだと信じられているのである。
前述の様な伝説と共に、神田の社をはじめ関東各地に将門が祀られた事は、将門が、如何に強く関東の人々の記憶の中で、尊敬され、同時に畏れられていたかを物語っていると思われる。
余談ではあるが、後の江戸時代、神田明神の氏子達は、南天の箸を使わず、又成田山へのお詣りにも行かなかったという。それは俵藤太が、成田山新勝寺に戦勝の祈願をし、将門との戦いに臨んだ上、将門の一命を落した御神矢が、南天の枝で作られた新勝寺の御神矢だったと言う、言い伝えがある為である。
(三) 神田神社の再興
時代は前後するが、仏教が伝来し、国教となった後、平安期を通して新しい思想が生まれた。それによって在来の神道と仏教が結びつけられ〔神仏習合〕、仏教の諸仏と神道の諸神が結びつけられ〔本地乗説〕、神社と寺院が一つにまとめられていった。神田の社の境内にも、日輪寺という天台宗の寺が建てられて、次第に天台宗の勢力が強くなっていった。この為、神田の社や首塚、その祭礼はしだいに重要視されなくなって、荒廃していった。
同時期、芝崎江門湊(えどみなと)〔当時はこういっていた〕の地は、天災が続き、凶作や不漁、疫病で苦しんでいたという。人々はこれを将門のたたりと考えた。これを鎮める為、人々の心を安んじる為、この地を訪れていた時宗二世遊行上人を中心に、社を再興し祭礼を復活させ、首塚を供養した。その時将門は、境内鎮守の明神として、神田の社に合祀された。徳治三年〔一三〇七年〕の事であり、これ以後、神田の社は、『神田明神』と呼ばれるようになり、人々に親しまれ厚い信奉を集めるに至るのである。
日本古来の神々が、仏教勢力に圧倒されていき、各地の神社、祠が荒廃していく中で、神田明神だけが、この様に復興されたのは、多分に将門の影響によるものである。
(四) 家康入府以後
鎌倉期以後、江戸氏・扇谷上杉氏・北條氏の各時代にも、神田明神に対しては信奉深く、信仰者も多く、徳川氏となってからは江戸総鎮守となるのである。
天正十八年〔一五九〇年〕八月一日徳川家康が、関東八州の領主として、三河岡崎より入府、この地を江戸と改めた。この日を八朔の討入といい、江戸期の重要な祝日となる。家康はさっそく城作り・町作りに取り掛かり、それに伴って神田明神も、今の駿河台に移り、社領として三十石を寄せられた。慶長八年〔一六〇三年〕のことであった。さらに、元和二年〔一六一六年〕現在の湯島台に遷された。神田明神の称はそのまま用いられた。首塚は、親藩家や譜代の家臣の屋敷内に入り、手厚く祀られた。又旧暦九月十五日の神田明神の祭礼には、町奉行の指図で、神輿を邸内に入れて神楽を盛んに奏して、将門の霊魂を供養した。
江戸城は、三代普請又は天下普請といわれ、総構え〔総縄張り〕が完成したのは、寛永十三年〔一六三六年〕のことで、その頃には町人町も次第に形成されて、全国から職人や商人が集って来て人口も急激に増え、又日本の総城下町として大名屋敷も城を囲むように作られた。江戸の町は、旭の昇るごとく日に日に繁栄していったのである。神田の地は、職人の町として全市中に対する役割りをはたしていった。
江戸期に入り神田明神の祭礼を『天下祭り』と称した。天下祭りとは、将軍が江戸総鎮守の神田明神と産土の神、山王日枝神社の祭りに参加したことによる名である。毎年、江戸っ子たちは、旧暦六月十五日と九月十五日が近づくとそわそわして落ち着かなくなる。これは麴町の日枝山王社の祭礼日と、神田明神の祭礼日で、江戸市中の人々がこぞって祝い騒ぐ日であった。将門を祀る神田明神に、人気と信仰が集ったといわれている。神田祭りの山車や神輿の巡行に活気があったのは、常に反骨精神を誇りに生きる江戸っ子の将門信仰によるものであったのであろうか。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
勇ましい掛け声に合わせて町々を練り歩く神輿の巡行は、まさに祭礼のシンボルであり、掛け声をかけて神輿を動かすことを、古来より『神輿振り』といって神威の発場を求めるためといわれる。神輿は文字通り神のコシで、奈良の大仏を建立する際、宇佐から八幡神を迎えるにあたり、紫色の輦輿にお乗せしたのが神輿の初めとされている。神社で神輿を用いるのは、一般に神幸祭の時であるが、現在では氏子の地区やその町々・村内を氏子がかついで練り歩き、その地区を神が巡行するものと考えられている。
神輿と同じように乗物である山車は、飾り立てた車、又は屋台のことで、これを祭礼の時曳き歩き、笛や太鼓で賑やかに祭礼の気を盛り上げるもので、山車をダシというのは、実は山車の屋根の上に突立てた山鉾の先端にあるしるしのもののことで、これを神の憑り代として棒げる信仰に由来する。つまり、山車は乗物であるといっても神輿のように、その中に神座があるのではなく、高い棒の先端に意味があるのである。神輿の方はほとんどの神社にあるが、山車は必ずしもすべての神社が所有しているものではない。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
神田明神の氏子町は、はじめ六十ケ町であったが、のち百余ケ町になっていく。祭礼は元和二年〔一六一六年〕迄は、すなわち芝崎にあった時迄は、神輿の舟渡御があって、小舟町神田屋庄左衛門宅前の御旅所迄神幸したが、この年をさかいに、山車や神輿中心の陸上の祭りとなっていくのである。
天和元年〔一六八一年〕以来、祭礼は町の負担を軽くするために、山王社と神田明神、両社一年交代ということになった。神田は、丑・卯・已・未・酉・亥の歳の九月十五日を中心にして、隔年に祭礼を行なった。元祿期以後は、各町は山車とそれに附随する附祭りの行列で神社を出発、天下祭り最大のイベント、江戸城繰込みを行った。将軍の観することでもあり、神田っ子の負けず嫌い、いや意地っ張りも手伝い、各町の山車は趣向をこらした金のかかったものであった。この様な山車は、神田明神の場合、三十六番が定例であったが、後年その数が増したとも言われている。このような山車や神輿が、笛や太鼓や鉦の囃子にあわせて賑かに練り歩き、江戸城へ繰り込むのは壮観であったろう。
神田祭りの場合、江戸城に入る御門は田安御門から城中に入り、城内では堀端にそって東北に進み、竹橋御門から城外に出て、大手前方面に進むのが順路であった。神田祭りは、元祿元年〔一六八八年〕から城内に繰り込んだと記録にある。将軍の上覧であるが、古くは手近かの多聞櫓などにのぼって見物した。正徳二年〔一七一二年〕に吹上の上覧所が設けられてからは、この場所が常設の上覧所となった。町人中心の祭りに将軍の見物場所を設けたところが、天下祭りといわれる由である。見物の時は、将軍だけでなく世子・奥方・旗本・諸大名等・はては奥女中迄が見物したのである。
祭礼の行列は、上覧所の正面の標識〔奉書紙で包み、金銀の水引きで結んだ長さ四尺程の杭〕のある所で止って、それぞれ各町の自慢の技を演じたりした。山車に続く踊り屋台といわれる屋台では、各町のよりぬきの町娘達によって美しいきらびやかな衣裳で踊りを演じた。中でも目立つ娘達は錦絵にもなったようである。又大担な所作で、人々をはらはらさせたものもあり、派手好きで茶目っ気の多い江戸の町人の気質を十二分に発揮したのである。江戸期の娯楽の少なかった時代だけに、祭礼のにぎわいは、人々を上は将軍から下は町人にいたるまで非常に楽しませたのであった。大奥から次の祭礼には、このようなものを踊ってほしいというような注文が出ることもあったといわれている。
このように神田祭りは、江戸を代表する行事であると共にその当時の一大文化でもあった。このことは今の私達の生活にもその名ごりが随所にあり、いかに多くの人々に楽しまれたかが分るし、時代を越えて私達の心をなごませて呉れる。又その時のことが、現代の私達の当然の生活習慣となっているものもあり、江戸文化のほのかな香りすら感じられるのである。
江戸の町も、江戸城も、又神田明神も、いく度かの火災・天災に見まわれているが、その度に、復興している。人々の信奉は力強く、神田明神を荒れたままにしてはおかなかったのである。
(五) 明治期から現代
慶応三年〔一八六七年〕将軍徳川慶喜は、大政を奉還し駿府〔静岡〕へと移った。そのため、人口もそれまで百三十万といわれた江戸の町は、六十万程に激減した。神田祭りも太政官政府により、江戸城繰り込みを禁止された。この為町会神輿や山車は、宮入りするだけの形に変化するのである。神田明神も明治元年准勅祭社、明治五年府社とされて、名称を神田神社と改められた。又明治七年少彦名命が、常陸国鹿島郡大洗・磯崎神社より分霊合祀された。
明治になってからは神田祭りも町々の変化により、急に衰微して行った。その上、明治七年から十年間、神田祭りが行なわれなかったのである。それは、祭神将門公の取扱いについて神社と氏子達の間で意志の疎通が、うまく行かない不幸な事があったからである。
やがて日本の文明開化も軌道にのり、外国の文化もどんどん入って来たのだが、こまった事もあった。それは町々に電線が張られ、又町に電車が走るようになって、それ迄自由だった各町の山車が巡行出来なくなってしまったのである。この為、山車は祭礼の時、各町に飾りとして置かれるだけになった。それ以後は各町から神輿だけが宮入りをしたのである。又明治からは、祭礼は五月十五日を中心に行われるようになった。これは、都内の交通事情と、それ迄の九月十五日ごろは、台風が多い季節であった為である。
その後、関東大震災で各町で持っていた山車等もほとんどが焼失してしまい、江戸の昔日の面影を残す町々も、完全に消えてしまうのである。神田神社も焼失してしまうのであるが、昭和九年に、日本で、神社としては最初の鉄筋コンクリート造りの社殿として復興された。この時、末社の平将門公も本殿に戻られたのである。
それから暗い戦争の時代もあったが、戦後、祭礼も復活した。しかし、高度成長の一時期、伝統的な文化等が、なおざりにされる風潮も見え、また、交通事情の悪化等から、神田祭りも昭和四十年を中心に、前後数年の間中断された時期もあった。しかし、明治百年祭を機に、以前のように隔年に行なわれている。特に昭和五十一年には、大震災で焼失したままだった隨神門も復興された。その後祭礼は、三日間から二日間になった。しかし現在、伝統文化や、信仰に対する日本人の関心が強くなっている時でもあり、神田神社でも参詣人は、年々増え続けている。今後益々活気を帯び、発展していく事を願うものである。
本サイトの掲載内容(画像、文章等)の一部及び全てについて、無断で複製、転載、転用、改変等の二次利用を固く禁じます。