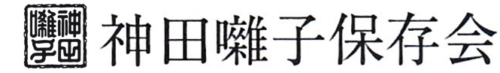神田囃子とは
江戸時代の祭り囃子が起源とされており、主に五人囃子(大太鼓・締め太鼓・篠笛・鉦)で演奏され、代表的な「神田囃子:素囃子」の曲目は「屋台・昇殿・鎌倉・四丁目(しちょうめ)・上がり屋台」からなる組曲となっています。その他に、神輿渡御に際しては「投げ合い」という賑やかな曲を演奏し神輿を盛り立てます。
神田囃子保存会とは
「神田囃子保存会」は、江戸の祭り囃子の伝統を受け継いで昭和2年(1927)に組織されました。
以来、神田明神や神田祭等でのお囃子の演奏等を中心に活動しており、東京都を代表する民俗芸能として国内外に紹介されています。
昭和28年(1953)には東京都民俗無形文化財の指定を受け、伝統の承継、発展と普及にカを注いでいます。
神田囃子は神田明神のお祀り事の時に奉納している、お祭り以外では聞く機会の少ない民俗芸能です。
こちらでは昭和57年(1982)に発行した「神田囃子保存会のあゆみ」を掲載しています。