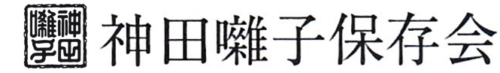| 西暦 | 年号 | 出来事 |
|---|---|---|
| 730 | 天平二年 | 神田神社創建される。 |
| 935 | 承平五年 | 平将門の乱(~950) |
| 940 | 天慶三年 | 平将門討死、神田神社に首塚が祀られる。 |
| 1192 | 建久三年 | 鎌倉、鶴ヶ岡八幡宮に於いて、五人囃子奉納。 |
| 1307 | 徳治三年 | 神田神社、首塚再興、神田明神となる。 |
| 1590 | 天正十八年 | 徳川家康入府。 |
| 1603 | 慶長八年 | 神田明神、芝崎より神田台(駿河台)に移る。 |
| 1616 | 元和二年 | 神田明神、湯島台へ移る。(現在地)神輿、山車中心の祭り。 |
| 1618 | 元和四年 | 神田明神の社殿造営される。(二代秀忠)この頃山車に附随する曲が伝えられていた。 |
| 1638 | 寛永十三年 | 江戸城完成。 |
| 1669 | 寛文九年 | 「里神楽」「太神楽」将軍家上覧。 |
| 1681 | 天和元年 | 神田祭、山王社と一年交代となる。 |
| 1688 | 元禄元年 | 祭礼行列はじめての江戸城繰込。(天下祭) |
| 1712 | 正徳二年 | 江戸城内吹上に祭礼の上覧所が設けられる。 |
| 享保年間 | 紀州より「和歌の浦囃子」が葛西地区に伝わり「葛西囃子」が江戸の祭りに参加し始めた。 | |
| 1867 | 慶応三年 | 大政奉還、神田明神准勅祭社となる。 |
| 1873 | 明治五年 | 神田明神、東京府、府社となる。この頃祭礼は五月十五日を中心として行われるようになる。 |
| 1875 | 明治七年 | これより十年間、氏子神田祭ボイコット。 |
| 1877 | 明治十年 | この頃、浅草の(植木屋)に於て「切り囃子」が作られた。 |
| 明治二十二年 | 青山啓之助、神田囃子保存会会長生まれる。(四月一日) | |
| 1902 | 明治三十五年 | 十五世家元、新井(屋根屋)喜三郎死去。 |
| その後長谷川金太郎十六世を継ぐ。 | ||
| さらにその後二世長谷川金太郎(金吾)が後を継ぐ。 | ||
| 1923 | 大正十二年 | 九月一日、関東大震災、神田明神、焼失 |
| この頃、二世長谷川金太郎を師に、青山啓之助のグループが、囃子の練習を始める。 | ||
| 1927 | 昭和二年 | 神田囃子保存会設立 |
| この頃、毎月一日と十五日に、神田明神に於て、囃子を奉納した。 | ||
| 1932 | 昭和七年 | 末社にあった、将門公が本殿に戻る。 |
| 1934 | 昭和九年 | 神田明神、震災で消失した、社殿が完成。 |
| 1937 | 昭和十二年 | 日中戦争が始まる。 |
| これ以後(昭和十三・四年頃)神田明神での囃子奉納中止。 | ||
| 1945 | 昭和二十年 | 第二次世界大戦終結。 |
| 長谷川金太郎(二代目)没。 | ||
| 1948 | 昭和二十三年 | この頃、各地で復興祭が行われる。 |
| 1949 | 昭和二十四年 | 五反田で、高井、近藤ら吉村から笛を習う。 |
| 1950 | 昭和二十五年 | 鼓友会の稽古始まる(無極亭) |
| 1951 | 昭和二十六年 | 都無形文化財の申請。 |
| 1952 | 昭和二十七年 | 無形文化財の指定が内定する。 |
| 八月趣意書が出される。 | ||
| 千代田区教育委員会より、神田囃子調査書が出される。 | ||
| 1953 | 昭和二十八年 | 九月十七日「保存に関する懇談会」(青山宅) |
| 九月二十四日「都芸能大会出演の為の稽古」(区役所三階公会堂) | ||
| 十月一日、文化放送、囃子録音(青山宅) | ||
| 十月二日「第二回東京都郷土芸能大会 」(日比谷公会堂) | ||
| 十月三十日、無形文化財指定、お披露目式(区役所三階公会堂) | ||
| 十一月三日神田囃子保存会、東京都無形文化財に指定される。 | ||
| 十一月四日、神田囃子保存会後援会設立準備委員会(区役所三階控室) | ||
| 1954 | 昭和二十九年 | 元日、この年から元日の奉納が始まる。 |
| 五月三十日、伝統芸術の会主催「神田囃子を聞く会」(如水会館二階日本間) | ||
| 八月五日「第八回全国リクリエーション大会」郷土芸能文化財の部。(仙台市公会堂、レジャーセンター) | ||
| 1956 | 昭和三十一年 | 四月、千代田区囃子教室(万世橋区民館・番町区民館) これ以後万世橋区民館での稽古がつづく。 |
| 1960 | 昭和三十五年 | 二代目金太郎十三回忌追善法要(市川) |
| 1962 | 昭和三十七年 | ビクターレコード録音。 |
| 1965 | 昭和四十年 | 一月四日、青山啓之助没。 |
| 二月、現会長青山栄二郎選出。 | ||
| 1966 | 昭和四十一年 | 六月、ハービーマンとの共演(東京厚生年金ホール) |
| 1968 | 昭和四十三年 | 稽古場が、万世橋区民館から神田明神に移る。 |
| 1970 | 昭和四十五年 | 三月「三越東都のれん老舗の会」神田囃子参加。これ以後毎年続く。 |
| 1972 | 昭和四十七年 | 十月十五日・十六日伊勢神宮遷宮式、神田囃子奉納。 この頃、鞆絵組結成。 |
| 1977 | 昭和五十二年 | 随神門完成。 |
| 1978 | 昭和五十三年 | 千代田区囃子教室第一期生の稽古始まる(区役所十階) |
| 1979 | 昭和五十四年 | 九月十五日国立大劇場、第三十一回民俗芸能公演「日本の太鼓」出演。 |
| 1982 | 昭和五十七年 | 十一月七日、保存会設立五十五周年・無形文化財指定三十周年記念式典。 |
「神田囃子保存会関連レコード」
<<コロンビア>> SA-3005, 3006, EP盤2枚組 1964年(S.39) 4月収録
曲目:カッコ入り囃子、投げ合い
笛 :上野 光之
調べ:青山 啓之助・松永 寅次郎
大胴:倉田 辰之助
鉦 :杉田 浩司郎
<<東芝>>JPO-1035, 25cmLPモノラル 収録年月不明
曲目:素囃子
神田囃子保存会 青山啓之助社中
笛 :上野 光之
調べ:小池 彦次郎・松永 寅次郎
大胴:青山 啓之助
鉦 :杉田 浩司郎
<<ビクター>> SJ-3004~2, 30cmLPステレオ 1962年10月
第17回芸術祭参加”江戸の神楽と祭囃子”収録(S.37)
曲目:素囃子
神田の囃子連中
笛 :上野 光之
調べ:小池 彦次郎・松永 寅次郎
大胴:青山 啓之助
鉦 :杉田 浩司郎
<<キング>> SFK-1001, 25cmLP 1962年(S.37)
曲目:素囃子、獅子、投げ合い、仁羽
神田囃子保存会
笛 :吉村 長吉
調べ:小林 信吉・鈴木 忠治
大胴:竹内 信治
鉦 :矢沢 政一
<<東芝>> TW-80007, 30cmLPステレオ 1976年(S.51)
昭和51年度芸術祭参加”神々の音楽"所収
曲目:屋台のみ
神田囃子保存会
笛 :小林 信吉
調べ:清水 康則・秋山 健太郎
大胴:小林 征治
鉦 :立野 喜久雄
本サイトの掲載内容(画像、文章等)の一部及び全てについて、無断で複製、転載、転用、改変等の二次利用を固く禁じます。