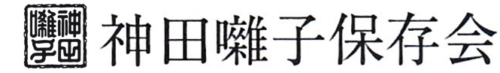第二章 祭り囃子の歴史
(一) 祭りの発生
(二) 祭り囃子の発生
(三) 祭り囃子の発展
(四) 切り囃子について
第二章 祭り囃子の歴史
(一) 祭りの発生
祭り囃子と限らず、古来より何かを打ち鳴すという儀式、又は、芸能は、その展開と要因が、神や精霊のもつ超人的な、魂に対する招聘の儀式に端を発しているといえる。
それは、人間は神の霊の一部が、肉体を持ったものだということで、その霊が、天より降りて来た時から、霊が離れる時までを人の一生とすると、考えられていた。
その為、一年に一回、その霊を天より呼んで、その霊に活力を与えてもらおうとしたのである。これを『祭り』といった。
その為に、色々な祭事に相応しい芸能を行なった。
まず、神霊の鎮魂のために、或いは、神慮を清しめる〔慰める〕ために『神楽』というものが奏じられた。
神楽には、宮中で行う『御神楽』と民衆の芸能の『里神楽』とに分けられる。
他に、田植の時や苗代田の土を均すような時に演じられた『田楽』や、その他『猿楽』も当時平安朝の中期以後、京都を中心に急速に各地に広まっていったものと思われる。
京都の祗園囃子などもその流れを汲むものと思われる。江戸の祭りも、祗園祭りを参考に山車や屋台などが作られたと言われている。自然にその囃子自体も何らかの形で伝わってきたかもしれない。
(二) 祭り囃子の発生
ここでは、まず神田祭りについて少し述べてから、そこで行なわれた囃子について考えてみたいと思う。古来より伝わってきた祭りが、十四世紀頃、江戸に疫病が流行したおり、その悪病追放の目的でガラリと様式が変わったといわれる。その当時、江戸に住む人々はその疫病は、平将門の霊が崇りをなした仕業と考えた。その霊を慰める為に遊行上人により、祭礼が復活された。
前章で述べたように、江戸の初期まで『水に全てを流す』という信仰から神田祭りは、毎年『舟祭り』を行なったそうである。竹橋から船で、小舟町の神田屋庄右衛門という者の宅前まで、神幸〔神の御渡り〕されていたそうである。
ところが、元和二年〔一六一六年〕の頃から祭の形態が次第に陸上の祭りへと変わってきて、美しい行列の形をとるようになった。つまり、神の分霊の神幸には美しい御輿にお乗せして、祭りの関係者が、その前後につき従って供奉するという行列の様式が出来上ってきたのである。そして、たまたま慶長五年〔一六〇〇年〕九月十五日、神田祭りが行なわれていた最中に徳川家康が、関ケ原の合戦に勝利をおさめたので徳川家は、これを吉事の祭りであるとして、代々神田明神を非常に厚く持て成すようになったのである。そこで、当時から現在に至るまで、その美しい山車や屋台で奏じられていた祭り囃子は、何時頃から発生して形造られたのだろうか。
この事に関しての、文献等が何一つ残されていないので、いわゆる憶測と数種の説があるのでここに紹介したい。
まず、最も古い起源の伝説としては、建久三年、源頼朝が征夷大将軍に任ぜられた折、鶴ケ岡八幡宮の社前で盛大な祭祀が行なわれた時、その道の達人六人が選ばれ、五人囃子を奉納したのが始まりであるという。しかし、これは後の世の人達が自分達の芸に、より古い起源を求めて権威づける作為であるように思う。
又、実際にそのような事があったとしても果して祭り囃子と、どれだけ、つながりがあるかは疑しい。
又、享保年間〔一七一六年〕に、紀州に『和歌の浦囃子』という大漁の時に船板を打ち鳴らした囃子があったそうである。それを、紀州の殿様が、江戸へ上がる時に持って来たといわれる。その当時、葛西地区の浦安、一之江等は海辺にあった。その為、その住民の全んどが、漁民であったと思われる。その為、紀州からもたらされた漁師の囃子である和歌の浦囃子が、この地方に伝えられた。それを、葛西金町村の鎮守香取明神〔葛西神社〕の神主・能勢環が、当時神社にあった里神楽と和歌の浦囃子とを手直しして『和歌囃子』なるものを作り若者を集めて教えたという。それが訛って『馬鹿囃子』と呼ばれるようになった。それが江戸の祭り囃子の元になったと言われている。
ところが、享保年間〔一七一六年頃〕に出来たと言われている馬鹿囃子であるが、神田明神の祭りが『舟祭り』であった時代は、千四百年代からであり、それが陸に上ったのが一六一六年、享保をさかのぼる事約百年も前の事である。そして将軍の上覧を仰ぐ『天下祭り』は、一六八八年で二十八年も前から初められていた事になる。
それでは、享保以前には囃子が付かなかったのだろうか。ところが前にも述べたように江戸の初期には、御輿神幸の際、祗園祭りの山鉾を真似た山車や屋台が既に作られていた。その上で演奏された囃子、又その囃子を奏した楽器が必ずあったと思われる。そこで、祗園祭りの形態が何らかの方法で伝わってきたのなら、祗園囃子も人からの言伝えで江戸に入って来たと考えられる。それは、まず楽器の編成から見ても頷けられる。
江戸の祭り囃子は、摺鉦・締め太鼓・大胴・笛という編成を成している。これは、祗園囃子の能管・鉦・締め太鼓、それに江戸の里神楽に使う大太鼓を加えたもので、江戸風に編成を工夫したということではないか。演奏された囃子も、祗園囃子の影響を受けているとは思うが、数百年の伝統ある京の人々と活気漲る新興都市、江戸の住人との気質の違いが当然出て、より活発な賑やかな曲が作られていったのではないだろうか。
又、当時関東地方では『里神楽』・『太神楽』等が大変流行しており、その祗園流囃子とそれらが互いに影響しあって、江戸流に一層洗練されていったと思われる。特に太神楽に於いては、現在の囃子に使われている曲目が多数入っている事からも、その事が裏付けられる。
太神楽には、尾州流と熱田流とがある。何時頃から江戸に入ってきたものかというと、徳川四代将軍家綱の寛文九年〔一六六九年〕正月に吹上の御庭で初めて上覧の栄を賜った。それが大変喜ばれ以後も毎年続けられた。その為これを期にこの神楽を演じた尾州・熱田の人々が多く江戸へ移住してきた。そして、享保年間には山王祭にも出るようになり、庶民の中にも深く溶け込み、又、祭り囃子とも深く係わる様になっていったと思われる。
(三) 祭り囃子の発展
最初は、江戸の祭りは山車や練物等が主流であった。それに付いて歩いた囃子は、俗に言う『静か物』とか『間物』と呼ばれる。比較的ゆっくりしている曲を主に奏していたと思われる。勿論、仁羽・四丁目等の曲も、その中に組まれていたと思う。特に祗園風、太神楽風、江戸囃子であった。
ところが、享保年間を過ぎると祭りの様相が変化してきた。鳥越・浅草三社等の御輿主体の祭りも、あちらこちらで始まるようになってきた。そこで、比較的賑やかな囃子が望まれるようになった。その頃、丁度江戸府内に広まり始めた馬鹿囃子なるものを多く取り入れるようになっていったと思われる。これがそもそも『屋台』と言われる物と思われる。それが伝統ある神田祭り・山王祭りにも参加していたが、将軍の上覧祭りという大変大きな祭りの為、なかなかその山車や屋台等で演奏する事が出来なかったので、より一層囃子の技を磨いていった。それが、今まで主流であった江戸囃子と馬鹿囃子との出合いである。
そこで、江戸囃子に馬鹿囃子が組み込まれていった物だと思う。これは、後に太神楽に馬鹿囃子を加えたという文献が残っている事からも察する事が出来る。
ここで、江戸囃子と言う現在の神田囃子の初歩の形が出来上がった訳である。江戸囃子の完成した当時は、娯楽と言う物が大変少なかった時代で、これが大変な流行を見せ江戸府内はもとより近郷にも急速に広まっていった。特に、葛西地区には数多くの囃子方が生まれた。
これはあくまでも推測である。
そこで、祭りに係わる一切を受けもつ役職を持った人が現われた。祭りが近づいて来ると、神田明神の氏子町内の役付けがその頭の所へ囃子の依頼にやって来て、その年の祭りの時に山車・屋台に乗る囃子方を頼みにくる。頼まれた頭は、何十組の中から一組を選び、その町内の主だった人の前で一曲演奏させ、彼らの耳に叶わなければ他の囃子方も呼んで、再び審査してもらった。そこで、合格してやっと晴れの神田祭りの山車や屋台に乗れたのである。
当時、囃子方には俗に言う祝儀というものは出ず、町内からは浴衣と一日三食の食事が支給されただけであった。遠くの村から、はるばるやって来て囃子をする割には少々報酬が少ないようであるが、それより神田何々町の山車に乗って囃子をやったと言う事実、つまり自分達の囃子が神田の旦那衆に認められたという事が、彼らにとって非常に名誉な事であった。
(四) 切り囃子について
さて、江戸時代から明治初期の祭り囃子はと言うと、現在の様な組曲ではなかったそうである。屋台なら屋台、昇殿なら昇殿のみを一曲づつ別々に取り替えひっ替え演奏していたらしい。これらの曲を総称して『江戸囃子』と言っていた。それが、明治十年頃に御府内の囃子方の主だった人々が、当時浅草にあった『植木屋』という貸席に集まった。
それは、今まで一つ一つ独立して演じられた曲を一つに組んでみたらどうかという話が持ち上がった為である。
大変粋な所に囃子方が集まり、二・三年の間、毎日毎日研究を重ね、今の様な組曲を作り上げたのである。それを『切囃子』と称した。それが、現在我々が普通に演じている組曲である。又、蛇の目返しからカッコ・神田丸等の間物を入れる編曲もこの時に決められた。その他、皮違いや曲打ちも研究され、祝獅子等の研究も始められた。
当時、集まった人達を紹介する。
神 田 市 川 鍋次郎 笛の人
小 村 井 藤次郎
新 善 寺 宗 与 市
神田だるま 満 吉
渋 江 村 浅 岡 金次郎
これらの人達によって『切囃子』が、作られたのである。
皮違い、曲打、祝獅子等、全部仕上がったのは明治十五年頃のことであった。これ以後、囃子を演じる時には、全てこの時に決められた形に基いて演じられ、現在もなお手直しされていないと言う事をとっても、ここに集まった人達が如何に囃子の大名人であるかと言う事が判る。ただただ先人達の努力、それを作り出した技倆には頭が下がる思いである。
今日、伝承されている江戸の囃子は、五人囃子といって大太鼓・締め太鼓・笛〔篠笛〕・鉦を以って一組としている。神田囃子の演奏の時の並び方は正面から見て、
笛〔トンビ〕
締め太鼓〔流〕
締め太鼓〔真〕
大 太 鼓〔大胴〕
鉦〔四助〕
この様に並び
演奏する素囃子〔地囃子〕の曲は、
初め、
打込み 〔朝日の昇る如くに〕
屋 台 〔やや賑やかに〕
昇 殿 〔おごそかに変化をつけて〕
鎌 倉 〔静かにゆっくりと神前にて手を打つ時と同じ拍子で〕
四丁目 〔早間で賑やかに〕
玉 〔四丁目の早さのまま自分の独創的な玉〔持玉〕を賑やかに〕
上り屋台〔最初の屋台より少し早間で、賑やかに〕
大上げ 〔締めくくりをしっかりと〕
これが、神田囃子でいう素囃子である。
その他に、間物と称してあまり演奏されないが素囃子の間に入れて演奏される曲がある。その時は、素囃子の順番が少し異なる。これらを、普通演奏しているが、神輿渡御に際しては『投げ合い』という曲を演ずる。神輿を、囃し立てるには、もってこいの賑やかな曲である。これに対し、お宮の鳳輦の巡行は、昔は牛で引いたもので行列の歩む速さに合わせて、その間ずっと緩やかな曲の『鎌倉』を演奏するのである。
木遣の時には、兄イの『エンヤリョウ』の遣り声に合わせて、打込みを入れ、屋台に入り短く切り上げ、すぐ鎌倉に入る。そのまま流して、最後屋台で終るというような事をした。昔、この木遣は、江戸府内にしか無くこの様に囃子を被せたのも神田の特色である。
囃子方が『祝獅子』と称して、獅子舞を伝えているのは太神楽の獅子舞を取り入れたものと思われる。正月とか祭りの時に、悪魔祓い或いは、世の中を祝ってしたものである。しかし、太神楽の様な神歌と弊束の舞が省かれている。囃子における獅子舞の手順を簡単に説明すると、まず、遠音神楽より入り狂に入る。そして眠りから再び狂いに房って終る。
又、この獅子舞の中に獅子が眠っている時に『もどき』という者が出てきて、悪ふざけをして眠っている獅子に『こより』で、鼻を突く一笑の場面がある。そして眠っている獅子を起して怒らせる役を演じる。この時は『仁羽』という曲を演奏する。これも、その演者によって、色々味がある芸を見せてくれる。
これを、獅子の鼻を、こよりで通すので『通し』とも呼ばれる。この時、もどきだけでなく『テンタ』と呼ばれるおかめの面をかぶった者も出て、なお一層おかしく演じることもある。
以上、簡単ではあるが、祭り囃子の歴史を解説してきた。庶民の中から生まれて、受け継がれて来たものなので、文献も無く口伝えの伝承が、僅かにあるのみであり、必らずしも正確であるとは言えまいが、取りあえず大略の歴史は判って頂けたのではないかと思う。
本サイトの掲載内容(画像、文章等)の一部及び全てについて、無断で複製、転載、転用、改変等の二次利用を固く禁じます。